 |
 |
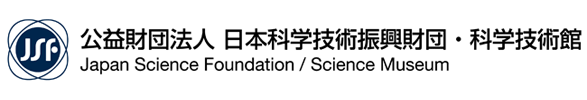
科学技術館開館50周年・日本科学技術振興財団設立55周年記念シンポジウム
『先進的「知」のネットワーク形成
『先進的「知」のネットワーク形成
~日本の未来のために必要な人材育成に向けて~』
2015年12月4日(金)
科学技術館サイエンスホール
(東京・北の丸)
科学技術館サイエンスホール
(東京・北の丸)

科学技術館

サイエンスホール
先の東京オリンピックが開催された1964年に開館した科学技術館は、以来50年にわたり主として青少年、親子連れ、家族連れを対象に体験型の展示手法を用いて科学技術・産業技術の振興に繋がる情報や知識の普及啓発活動を展開し、理工・科学・技術系に携わる創造的人財の育成に努めてきました。これまでの入館者累計はまもなく3000万人に達しようとしています。
公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館では、昨年・今年の2年間にわたり科学技術館開館50周年記念事業(標語:NEXT50)を展開してまいりました。本シンポジウムは、2年間の記念事業のしめくくりとして、今後、科学技術館を含む全国の科学館が産官学と連携し科学技術の振興と理解増進をいかに進めていくか様々な視点で議論を交わし具体的な方向性につなげたいと考えています。
▲このページのトップへ
| 名 称: | 科学技術館開館50周年・日本科学技術振興財団設立55周年記念シンポジウム 『先進的「知」のネットワーク形成~日本の未来のために必要な人材育成に向けて~』 |
| 日 時: | 2015年12月4日(金)13時30分~17時30分 |
| 場 所: | 科学技術館サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園2番1号) 科学技術館への交通案合 【東京メトロ東西線】「竹橋」駅下車徒歩約550m 「九段下」駅下車徒歩約800m 【東京メトロ半蔵門線】「九段下」駅下車徒歩約800m 【都営地下鉄新宿線】「九段下」駅下車徒歩約800m |
| 定 員: | 一般400名(定員になり次第、締め切らせていただきます。) |
| 参加費: | 無料。 なお、交流会への参加費は、一般1,000円、学生500円です。 |
| 主 催: | 公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館 |
| 後 援: | 文部科学省、経済産業省、一般社団法人日本経済団体連合会、 日本商工会議所、 全国科学博物館協議会、 全国科学館連携協議会、読売新聞社 |
▲このページのトップへ
▲このページのトップへ
| 13:30 | 開会 |
| 13:30~13:45 | 開催にあたって「科学館への期待・科学館の果たすべき役割」 科学技術館館長 野依 良治 |
| 13:45~14:15 | 基調講演Ⅰ 「我が国の科学技術イノベーション戦略」 久間 和生 総合科学技術・イノベーション会議議員 |
| 14:15~14:45 | 基調講演Ⅱ 「科学技術人材を育てる」 有馬 朗人 学校法人根津育英会武蔵学園長(前科学技術館館長) |
| 14:45~15:30 | 特別講演 「未来予測と求められる科学技術人材」 田中 栄 株式会社アクアビット代表取締役 |
| 15:30~15:45 | 休憩(15分) |
| 15:45~17:15 | パネルディスカッション 「先進的“知”のネットワークに向けて」 ファシリテータ 植木 勉 公益財団法人日本科学技術振興財団 常務理事 |
| パネリスト ①亀田 和宏 大日本印刷株式会社 ABセンターマーケティング本部 ソーシャルイノベーション研究所所長 タイトル:未来のあたりまえをつくる
概 要:DNPは先進の印刷技術と情報技術を最大限に活かし、「知とコミュニケーション」「食とヘルスケア」「住まいとモビリティ」「環境とエネルギー」を4つの成長領域と定め、生活者や企業にとって不可欠な製品やサービスの創出に取り組んでいます。安全で心地良いコミュニケーション、文化を育む取り組みなど、社会が求めるものをビジネスにしていくことで、「未来のあたりまえ」を実現して行きます。
②樋口 邦史 富士ゼロックス株式会社 営業計画部復興推進室室長遠野みらい創りカレッジ総合プロデューサー タイトル:地域社会の未来をひらく~みらい創り活動の実践~
概 要:東日本大震災の被災地を地域が一丸となって後方から支援した遠野市と、復興支援を継続的な活動として実践する当社が、行政・企業組織の枠組みを超えて“触れ合うように学ぶ場”として設立したのが「遠野みらい創りカレッジ」。昨年度は、域内外から延べ約4,000名の方々が学びを目的に訪れ、農家民泊を中心に1,800名が宿泊。
遠野市の交流人口拡大を支援することとなりました。本年度は、“交流”“暮らしと文化”“産業創造”の3つの基幹プログラが開講され、新たな事業や雇用を生み出すための対話や議論が日々なされています。本日の発表では、カレッジ設立の経緯と、実践されているプログラム「みらい創り活動」そして、地域社会の未来をひらくマネジメントについて紹介します。
③小倉 康 埼玉大学教育学部准教授 タイトル:科学技術人材育成~理科教育の視点から~
概 要:子どもたちに、将来、科学技術の発展に関わりたいという意欲を抱かせるには、学校で教えられる理科ではほど遠い現状です。理科の基礎的基本的な知識と技能を習得させ、それを使って答えのある問題が解けるようにすることが、理科を教える教員の主たる職務となっています。実社会で、未知の領域に新たな答えを見つけようと科学技術の研究開発に日々勤しむ人々の世界の魅力を知らないまま、高校生の大半は理数が嫌いになり、文系に進学することになります。この問題は、学校だけの責任ではなく、科学技術の世界との協働によって解決すべきです。具体例を紹介しながら、子どもたちと彼らの教員が実社会の科学技術に触れ、その魅力を実感できる機会を充実させることを訴えていきたい。
④針谷 亜希子 千葉市科学館教育普及グループ企画戦略チームタイトル:博物館がつなぐ地域の「知」と「人」
~科学フェスタと科学クラブ 二つの連携企画を事例に~
概 要:シンポジウムのテーマとなっている、知のネットワーク構築とその担い手の人材育成という視点から、当館で行ったJST支援事業「科学するこころの伝達とはぐくみ-日常的な科学フォーラムの創成に向けて」の取り組みと、その中で生まれた科学フォーラムの萌芽について報告します。実務担当者の立場から、千葉市の企業・大学・学校・教育委員会・研究所・NPO法人など様々な機関を巻き込んで行う「千葉市科学フェスタ」、市内の動物園・博物館・図書館・学校などが連携して行う「ちば生きもの科学クラブ」という二つの事例をもとに、地域の博物館における“知と人のつながり”作りについて紹介します。
| |
| 17:15 | 閉会挨拶:日本科学技術振興財団専務理事 藤川 淳一 |
| 17:30~18:30 | 交流会(科学技術館パークレストラン) |
▲このページのトップへ
公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館
経営企画・総務室「記念シンポジウム」事務局
〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2番1号
電子メール:info5055@jsf.or.jp
URL:http://www2.jsf.or.jp/5055sympo/index.html
▲このページのトップへ
| 財団の概要 |
| 財団について |
| 賛助会員制度 |
| 賛助会員一覧 |
| 公開情報 |
| 交通アクセス |
| 経営企画 |
| 経営企画・総務室 経営企画グループ |
| 公益事業部門 |
| 科学技術館運営部 |
| 人財育成・施設開発部 人財育成グループ 企画開発グループ |
| 公益施設開発部 |
| 航空記念館運営部 |
| ハンセン病資料館運営部 |
| 収益事業部門 |
| 情報システム部 |
| 施設運営部 |
| 広報誌等 |
| 広報誌ダウンロード |
| 各種報告書ダウンロード |
 |
| 関連団体・リンク |
| 著作権・リンクについて |
| 個人情報保護方針 |
(C)2013 Japan Science Foundation All Rights Reserved. |

